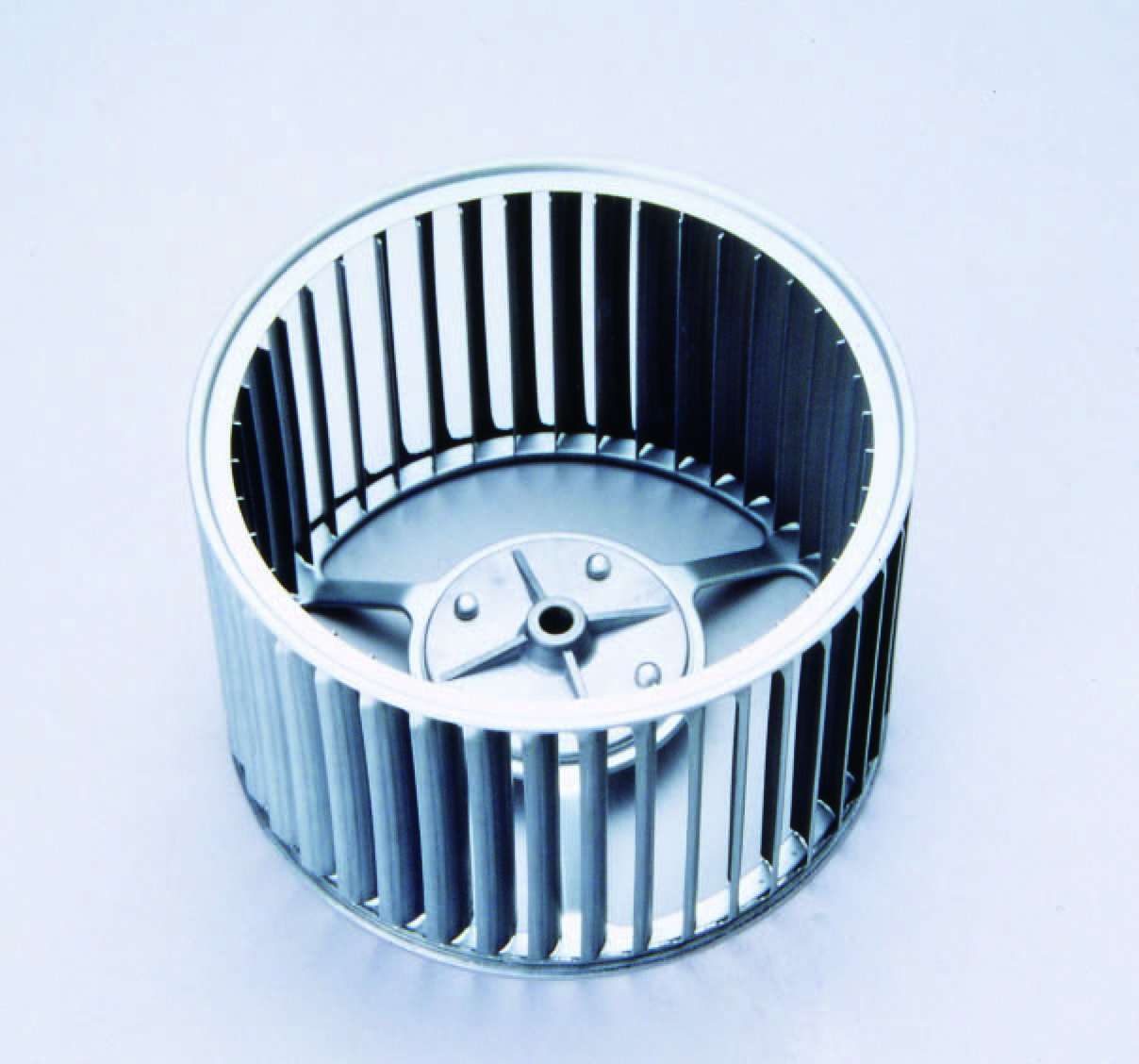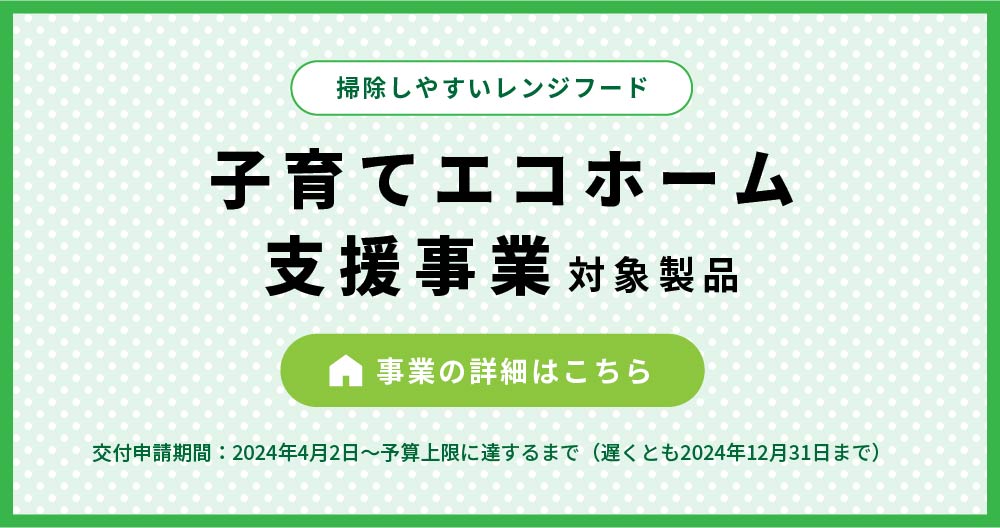変わったドリッパーでお茶を淹れてみた

2023年4月18日
- この記事をシェアする
-

-


この記事のURLをコピーする URL copied
皆様お茶を淹れて飲まれますでしょうか?
私はあまり急須などでお茶を淹れる習慣がないのですが、
今回紹介するのは、お茶をドリッパーで淹れるという一風変わった商品を紹介いたします。

お茶について
皆様ご存じかとは思いますが、チャノキという植物から採れた葉っぱや茎から作られる飲み物で、発酵工程を行ったものを紅茶、発酵工程を行わなかったものを緑茶と呼びます。
日本ではあまり流通されているイメージのない中国茶ですが、お茶の生産で世界4割を占める中国では、緑茶、白茶、黄茶、烏龍茶、紅茶、黒茶の6種類で区別されており、下記のような特徴を持ちます。
- ・緑茶・・・摘採後、酵素反応が始まらないうちに速やかに釜炒りする。中国での生産は60%(出典元 伊藤園)
- ・白茶・・・中国福建省特産の希少なお茶。摘採後、火入れを行わず自然乾燥させる。
- ・黄茶・・・摘採後、加熱処理を行う。ポリフェノールやクロロフィル(葉緑素)を酸化する過程で黄色くなる。
- ・烏龍茶・・・茶葉の発酵途中で加熱することで発酵を止めた半発酵茶であり、品種は800近くある。
- ・紅茶・・・温度、湿度、通気を調整し、茶葉が赤褐色になるまで反応を行わせる。
最大の生産国はインド。 - ・黒茶・・・中国安徽省、四川省、雲南省で作られ、日本では雲南省産のプーアル茶が最も有名。微生物による発酵を行うことが特徴的。
成分と効能
コーヒーやお茶にはカフェインが多く含まれることは良く知られておりますが、お茶にはタンニン(カテキン類)・テアニン・ビタミンCがコーヒーより多く含まれております。
特に野菜が枯渇している地域・国などでは、お茶を飲む習慣がある。(出典元 伊藤園)
ドリッパーでお茶!?刻音 沈殿抽出式ティードリッパーの紹介
基本的なお茶の淹れ方は、急須に茶葉を入れて、お湯を注ぎ抽出する方法が一般的だが、
今回紹介する商品は、「沈殿抽出式」という方法を採用しており、茶葉をフィルターとして日本茶をドリップする方法です。
刻音 沈殿抽出式ティードリッパーの特徴
1、沈殿抽出式
ペーパーレスフィルターやステンレスの茶こしなどを使用せず、日本茶をドリップする方法で、お茶の繊細な個性(香り・うまみ・渋み)をしっかりと出してくれる茶器です。
また、茶葉自体をろ過フィルターにするので、お湯が注がれた茶葉は、本体の中でゆっくりと開き、その後沈殿することで、何層にも重なり「ろ過フィルター」のようになります。
そのため、抽出されたお茶は重力にしたがってサーバーに落ちて行くので、雑味・微細な茶葉はしっかりろ過され、クリアかつ味わい深いお茶を抽出できます。

2、金属不使用
金属が用いられているパーツがなく、本体とツマミは「半陶器」、サーバーは「耐熱ガラス」で出来ており、金属を使わないことでお茶の自然な風味を保ちます。

3、お茶を淹れるプロセスを楽しめる
・デザイン
砂時計のようなデザインで、お茶が抽出される様子自体も楽しむことができます。




ゆったりとした時の流れを感じることができます。
・抽出音
お湯を淹れると「ぽちゃぽちゃ」としずくが落ちる音が聞こえてきて、そのあと、茶葉が広がっていく音が聞こえてきて、最後にツマミを引くと川のせせらぎのような音が聞こえてきます。
お茶の味だけでなく、お茶を淹れるというプロセスも楽しめる。という点が非常に今までにない抽出器具だと思います。
使用方法
①本体につまみをセットする際に、それぞれのパーツにある「●」を合わせる。
※合わせていないと茶葉が落ちてしまう要因になります。

②一杯あたり4~6gの茶葉を入れる。
③お湯を注ぐ前に、茶葉が浸るくらい(大さじ1杯ほど)のお湯で、30秒~1分ほど蒸らし、水分を含ませる。
この記事を書いた人
2023年4月18日
- この記事をシェアする
-

-


この記事のURLをコピーする URL copied